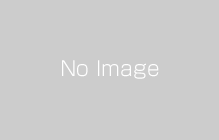温度の表し方として一般的なものは「摂氏温度」ですが、実はほかにもあります。
少し気になったので、調べてみました。
現在使われている温度の表し方のうち、次の3つが代表的なものです。
1.摂氏温度
スウェーデンの天文学者アンデルス・セルシウス(Anders Celsius)が1742年に考案したもので、現在、世界中でもっともよく使われています。単位は、℃を使います。
1気圧のもとで氷が溶ける温度を0℃、水が沸騰する温度を100℃として、その間を100 等分したものを1度の温度間隔とします。
2.華氏温度
ドイツの物理学者ガブリエル・ファーレンハイト(Gabriel Daniel Fahrenheit)が1724年に考案したもので、現在でもアメリカ、イギリス両国ではよく使われています。単位は、℉を使います。
1気圧のもとで氷が溶ける温度を32℉、水が沸騰する温度を212℉として、その間を180 等分したものを1度の温度間隔とします。
華氏温度では人間の平熱37℃が98.6 ℉となります。
3.絶対温度
イギリスの物理学者ケルビン男爵(Lord Kelvin) が1848年に考案したもので、高校の物理や化学で登場します。単位は、Kを使います。
分子や原子の熱運動が停止する温度を絶対零度といいますが、これは摂氏温度では-273.15℃であり、絶対温度では0(ゼロ)Kです。
また、1度の温度間隔は、摂氏温度と等しい間隔です。
摂氏温度t(℃)と絶対温度T(K)の関係は、次の式の通りです。
T=t+273.15
アルゴでは、3/25(水)~4/4(土)の期間、春期講習会を行います。
春期講習期間中は、13時から22時まで開校します。
お問合せは 0120-25-0010まで。
ご連絡をお待ちしています。