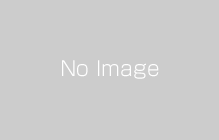9月もおしまいに近づいて、だんだん涼しくなってきましたね。
すっかり秋を実感するようになりましたが、秋の楽しみの一つと言えば、「紅葉狩り」ですね。
そこで今日は、「紅葉の科学」についてお話しします。
春から夏にかけて、樹木の葉は緑色に見えます。
この緑は「クロロフィル」という色素に起因します。
クロロフィルは、太陽の光を構成している赤・緑・青の三色の中から、赤と青の光を吸収します。
緑の光は吸収されずに反射されるので、葉は緑色に見えるのです。
秋に葉が黄色くなる現象には、クロロフィルの他に葉に含まれている「カロチン」という色素が関わっています。
カロチンは、クロロフィルよりずっと安定している物質です。
そのため、気温が低くなってクロロフィルが合成されにくくなる秋には、カロチンがクロロフィルよりも多く残ります。
このカロチンは、青と青緑の光を吸収します。
吸収されない赤と赤味を帯びた緑色が反射されるため、葉は黄色に見えるのです。
紅葉の紅い色には、「アントシアニン」と呼ばれる色素が関係しています。
アントシアニンは、熟したリンゴやブドウの皮の赤色の原因となるものです。
アントシアニンは、細胞液中の糖とある種のタンパク質間の反応により生成されます。
秋には葉に糖が過剰となり、アントシアニンが生成されやすくなります。
アントシアニンは、青、青緑、そして緑の光を吸収するため、赤い光が反射され、葉が赤く見えるようになります。
植物の種類によって色づき方が異なるのも、これらの色素が影響しています。
いちょう、プラタナス、カバの木やヒッコリーの葉はカロチンを多く含んでいるため、クロロフィルが生成されなくなると黄色くなります。
かえでやツタは、糖分が異常に増えやすいため、アントシアニンがより多く生成されて、紅く見えます。
なお、この記事は地層科学研究所のHPの記事を参考に書きましたので、さらに詳しく知りたい方は
https://www.geolab.jp/science/2002/11/science-005.php
をご参照ください。